
適応障害を繰り返すのはなぜ?再発のサインと今すぐできる対策を解説
「職場復帰したら適応障害が再発するんじゃないか?」、「適応障害が再発しないためににはどうしたらいいんだろう?」という不安を抱える人は少なくありません。
適応障害の再発は決して珍しいことではないですが、適切な対策により再発のリスクを減らすことが可能です。本記事では、適応障害が再発する理由、すぐに始められる再発予防策について専門医の知見を交えながら解説します。

医師
石飛信
国立大学医学部を卒業後、母校の精神科医局に入局。臨床医、研究職を経て、現在は単科精神科病院で勤務。医療ライターとして医療系記事の執筆も行っている。精神保健指定医、日本精神神経学会専門医・指導医、子どものこころ専門医、医学博士。
適応障害が繰り返されるのは珍しいことではない
適応障害は再発率が高い疾患として知られています。
厚生労働省の調査研究によると、適応障害も含むメンタルヘルス不調で休職し復職した人のうち「1年以内に57.4%、2年以内に76.5%が再び病気休職した」と報告されています[1]。また、この調査では職場環境やストレス要因の改善が不十分な場合に再発率がとくに高まることが指摘されています。

適応障害が繰り返しやすい4つの理由
適応障害が繰り返しやすい理由について以下に解説します。
1. ストレスの根本原因が解決されていない
適応障害の原因となった職場や家庭でのストレスが十分改善されていないと、一時的な休養や治療で症状が改善したように思えても、もとの環境に戻ることで再び症状が現れやすくなります。
例えば、適応障害の原因となった過剰な業務負担や職場の人間関係などがほとんど変わっていない職場に復職する場合などがあげられます。
2. ストレス対処法が十分身についていない
環境調整でストレス要因をうまく取り除けた場合でも、再び新たなストレス要因に向き合わなければならないときがあります。このような場合に、ストレスへの対処法が十分に身についていないと再発の一因になります。自身のストレスへの対応力をなるべく高め、再び適応障害にならないように工夫していくことが大切です。
その一つの方法として、認知行動療法(CBT: Cognitive Behavioral Therapy)があります[2]。CBTでは、医師や臨床心理士とのカウンセリングを通して、自分自身の思考や行動パターンに気づき、少しずつ考え方を変えていきます。
例えば、「失敗したらどうしよう」というネガティブな思考を、「失敗しても大丈夫」という現実に即した考え方に変えていく練習をします。CBTにより、ストレス要因に対する考え方や対処法を修正していくことで、ストレス要因への適応力を高められる可能性があります。
3. 回復期間が不十分
心身の回復期間が十分でないままストレスの多い環境に戻ると、再発リスクが高まります。休養により症状がある程度落ち着き、一見元気な頃に回復したように見えても、まだ回復の途中であることが多いです。そのため、焦らず自分のペースで生活リズムや体力を少しずつ戻し、余裕のある状態で再スタートすることが重要です。
4. 発達障害特性への対応不足
ADHDやASDなどの発達障害を持つ方への合理的配慮がなされていないことも、適応障害が繰り返しやすい要因となります。これらの障害特性があると、環境の変化や対人関係で大きなストレスを感じやすいため、個々の障害特性に応じたサポートや職場環境の工夫が欠かせません。
発達障害があることに本人が気づいていない場合も多いので、もし発達障害がある可能性を周囲や家族から指摘された場合は、医師にもよく相談した上で、自分に合った対策を取ることが再発防止につながります。
適応障害再発の3つのサイン
適応障害の症状は多岐にわたり、症状の現れ方はその人の考え方や置かれた環境、ストレスの大きさによって異なります。症状はおおまかに以下の3つのカテゴリー(身体症状・精神症状・行動面の症状)に分けられます。適応障害になったことがある方は、過去に経験した症状が再発時にも現れることが多いです。

ストレスが強まった時には、自身が過去に経験した症状がぶりかえしていないかをセルフモニタリングすることが大切です。再発のサインがあった場合は、十分休息を取るよう心がけ、上司や同僚、医師に早めに相談しましょう。
身体症状
- 眠れない、もしくは寝過ぎてしまう
- 食欲がおちる、または逆に過食気味になる
- 胸がドキドキする
- 吐き気やめまいがする
- 体がふるえる
- 頭痛 など
精神症状
- 気分が落ち込む
- 不安で落ち着かない
- 神経質になる
- 焦ってばかりになる
- 意欲・興味が低下する
- 思考力・集中力が低下する など
行動面の症状
- お酒やタバコの量が増える
- 涙もろくなる
- 浪費が増える
- 周囲とのトラブルが増える
- 暴飲暴食が止められない
- ストレスが溜まりモノに当たる など
今すぐ始められる再発防止策
適応障害は「一度よくなったから安心」というものではなく、再発防止に向けた長期的なセルフケアが求められます。適応障害の再発防止には、日常生活の小さな工夫から専門的な支援まで多角的なアプローチを行うことが大切です。ここでは再発を防ぐための具体的な方法を解説します。
生活リズムの小さな変化から始める
再発防止には睡眠や食生活などの生活リズムを整えることが重要です。たとえば、睡眠覚醒リズムが乱れている場合には、毎朝の起床時間をいきなり大きく早めるのではなく、「15分ずつ段階的に調整する」など負担なくできることから始めましょう。
また、「1日1回だけでもバランスのよい食事にする」、「無理なくできる範囲のストレッチや5分の散歩を生活に組み込む」ことからスタートするのもよいでしょう。
ストレス要因の特定と環境調整
再発の多くは、自身が処理しきれないストレスを再び抱えてしまうことに起因します。まずは、自分が何にストレスを感じ、不安や苛立ちを感じるかを簡単に書き出してみましょう。そうすることで漠然と認識していたストレス要因が明確になるでしょう。

ストレス要因が明確化すれば、上司や人事担当者と相談しながらストレスとなった業務や配属場所の調整を可能な範囲ですすめましょう。ストレス要因の種類によっては完全に取り除くことが難しい場合もあると思いますので、ストレスを解消するためにプライベートな空間や自分だけの「ホッとできる時間」を確保することも大切です。
セルフモニタリングを習慣づける
セルフモニタリングとは、「自分自身の状態(気分・生活リズム・体調・ストレスへの反応など)を具体的に観察、記録し、定期的に振り返る行為」を指し、適応障害の再発予防における有効性が示されています[3]。
たとえば「ストレス度合いを10段階で評価して日々記録する」「週末に一度だけ振り返り、今週の良かった点と困った点を書き出す」ことで、自身の体調変化に気付きやすくなります。
日々の気分・体調・生活リズムを記録することで「ストレス過多や体調不良の早期発見」「再発サインへの迅速な対処」が可能になり、医師や支援者への相談につながりやすくなります。
医療機関との連携で再発リスクを下げる
主治医との相談方法
再発リスクを早めに察知し、適切な対応につなげるためには、主治医との定期的なコミュニケーションが大切です。再発のサインと考えられる自覚症状があったり、日常生活や仕事上の違和感を感じたりした時点で、自己判断せず医師に早めに相談することが大切です。
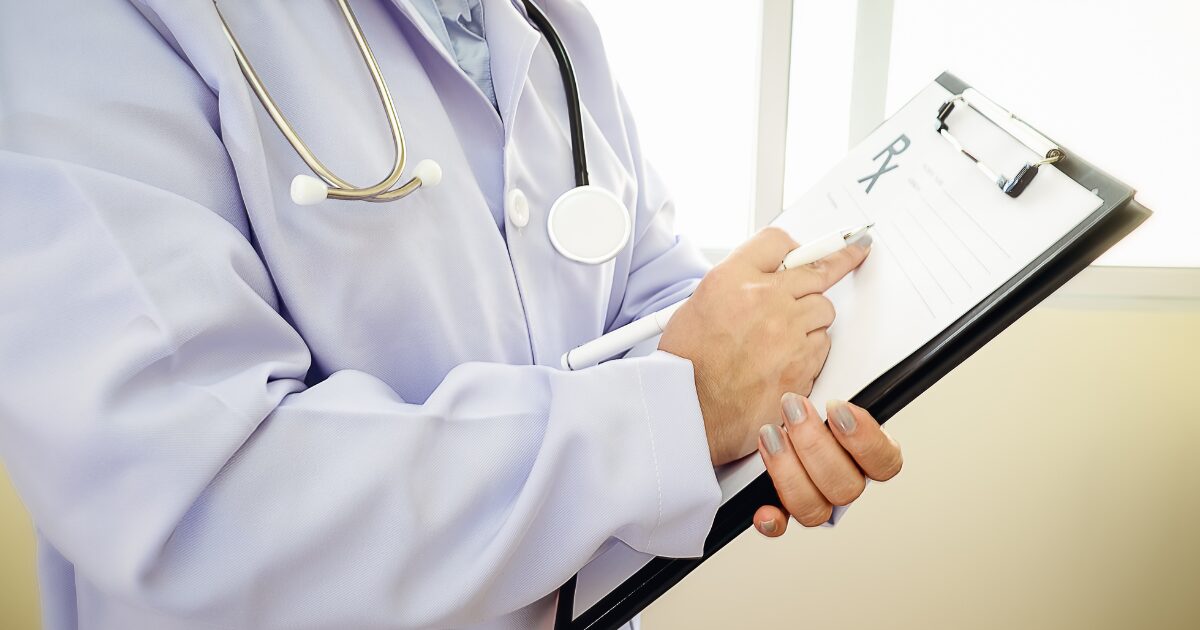
睡眠状況や食欲の変化、日々の気分や行動の変化を具体的にメモしておくことで、医師も客観的に状況を判断しやすくなり、治療方針の最適化に役立ちます。
適応障害そのものを治す薬はありませんが、不眠や不安感といった症状に対し薬物療法を行うことで、再発予防に取り組む余裕が生まれますので、状況に応じて薬物療法についても遠慮なく医師に相談しましょう。
心理療法やリワークプログラムの活用
再発予防に向けて、CBTなどの心理療法やリワーク(職場復帰支援)プログラムが行われることがあります。CBTでは、医師や臨床心理士とのカウンセリングを通して、適応障害の原因となったストレス要因に対する自分自身の思考や行動パターンに気づき、少しずつ考え方を変えていきます。これにより、同じようなストレスを受けた時の不安や落ち込みを軽減し再発リスクを下げることが期待できます。
リワークプログラムは、休職や離職をした人が社会復帰・職場復帰する際のための訓練プログラムです。生活リズム調整、職場でのストレスの対処訓練、模擬就労、集団での課題実施などを通じて、実社会に近い状況下で「無理のないペース」で徐々に自信と仕事能力を回復することができます。
このように、医療機関との定期的な連携、CBT、リワークプログラムなど多角的なアプローチが、適応障害の再発リスク軽減に役立ちます。一人で抱え込まず、気になった時点で受診することが回復の近道です。
CBTにより、ストレス要因に対する考え方や対処法を修正していくことで、ストレス要因への適応力を高められる可能性があります。
当メディアを運営するマインドバディでは、オンラインでCBTを専門としたカウンセリングを提供しています。専門家と一緒にストレス要因への適応力を高めてみたい方は詳細を確認してみてください。
まとめ
適応障害の再発は決して珍しいことではありませんが、適切な対策を講じることで再発リスクを減らすことが可能です。再発防止には、生活リズムの改善やストレス要因の特定と対処、セルフモニタリングによる心身の健康管理が大切です。
また、一人で抱え込まず、専門医やカウンセラーと連携し、認知行動療法やリワークプログラムを活用することも再発防止に役立つでしょう。焦らず、周囲の力をかりながら自分のペースで回復を目指しましょう。
参考文献
[1]職場におけるメンタルヘルス不調者の事例性に着目した支援方策に関する研究(厚生労働省)平成27年度~29年度 総合研究報告書
[2]認知行動療法(CBT)とは|認知行動療法センター
[3]職場復帰支援の実態等に関する調査研究(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(障害者職業総合センター)





