
適応障害になりやすい人の性格とは?真面目で責任感の強い人が注意すべきストレス対策
現代社会で生活する私たちは、職場や学校、家庭などで日々さまざまなストレスにさらされています。ストレスが原因で心身のバランスを崩し、日常生活に支障をきたしてしまう状態を適応障害といいます[1]。ストレスが明確なきっかけとなり、気分の落ち込みや不安、不眠、行動面の変化など様々な症状が現れ、日常生活に大きな影響を及ぼします。
適応障害は、特別な人がかかる病気ではありません。厚生労働省の調査でも、適応障害の患者数は年々増加しており、身近な病気といえるでしょう[2]。この記事では、適応障害の基本的な症状や原因、そして科学的根拠に基づいた治療法や予防策について、専門家の知見を交えながら解説します。ストレスとの賢い付き合い方を知り、心身の健康を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

医師
石飛信
国立大学医学部を卒業後、母校の精神科医局に入局。臨床医、研究職を経て、現在は単科精神科病院で勤務。医療ライターとして医療系記事の執筆も行っている。精神保健指定医、日本精神神経学会専門医・指導医、子どものこころ専門医、医学博士。
適応障害とは?基本的な症状と特徴
適応障害の定義と診断基準
適応障害は、ストレス要因(過重労働、転職、異動、進学、家庭の問題など)がきっかけとなり、心身や行動面にさまざまな症状が現れる病気です[1]。ストレスの原因が明確で、通常はそのストレスにさらされてから1〜3カ月以内に症状が発症し、日常生活や仕事、学業などに大きな支障をきたします。

適応障害は、精神疾患の診断基準の一つである「DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)」において、ストレス関連障害群の一つとして位置づけられています。その診断基準は、以下の要件を満たすこととされています。
- 特定のストレス要因への反応である: 仕事の異動、人間関係の変化、病気や災害など、明確なストレス要因が存在する。
- ストレス要因への不適応的な反応: ストレス要因に曝露されてから3か月以内に、症状が出現すること。また、その症状が、一般的なストレス反応の範囲を超えて、日常生活や社会生活に著しい支障をきたしている。
- 持続期間: ストレス要因が解消されると、通常6か月以内に症状が軽快する。
- 他の精神疾患(うつ病など)では説明できない。
この診断基準からもわかるように、適応障害はストレス要因との関連性が非常に強いことが特徴です。ストレスの原因がなくなれば、症状も改善に向かう可能性が高いとされています。
適応障害の主な症状(精神的・身体的・行動面)
適応障害の症状は多岐にわたり、症状の現れ方はその人の考え方や置かれた環境、ストレスの大きさによって異なります。おおまかに、以下の3つのカテゴリーに分けられます。
身体症状
- 眠れない、もしくは寝過ぎてしまう
- 食欲がおちる、または逆に過食気味になる
- 胸がドキドキする
- 吐き気やめまいがする
- 体がふるえる
- 頭痛 など
精神症状
- 気分が落ち込む
- 不安で落ち着かない
- 神経質になる
- 焦ってばかりになる
- 意欲・興味が低下する
- 思考力・集中力が低下する など
行動面の症状
- お酒やタバコの量が増える
- 涙もろくなる
- 浪費が増える
- 周囲とのトラブルが増える
- 暴飲暴食が止められない
- ストレスが溜まりモノに当たる など
これらの症状は、一般的に病気でない方にもあらわれる症状といえます。しかし、適応障害の場合、症状の程度が強く、日常生活に支障をきたすレベルになります。ストレスに耐えきれなくなった心と身体が発するSOSと考えられます。
どうして適応障害になるのか?
適応障害になるかどうかは、ストレス要因の種類や程度に加え、そのストレス要因に対する個人の対応力や考え方が大きく関与します。
適応障害につながりやすいストレス要因
適応障害のきっかけになるストレス要因として、下記のようなものがあげられます。誰もが経験しうるような出来事が多く、喜ばしいと考えられる出来事(昇進や子どもの誕生など)がストレス要因となることもあります。
職場や学校でのストレス要因
- 転校や進学
- 転職、転勤、部署移動
- 責任のある役職への昇進
- 同級生や同僚、上司などとの人間関係のトラブル
- パワーハラスメントやセクシャルハラスメント
- 過重労働 など
プライベートでのストレス要因
- 両親や配偶者、子ども、親戚などの家族関係の不和
- 子育ての負担
- 引っ越しによる環境の変化
- 経済的不安や家計のプレッシャー
- 長期的な治療を要する病気
- 台風や地震などの災害 など
ストレス要因に対する個人の対応力や考え方
同じようなストレスを受けても、適応障害になる人とならない人がいます。これは、直面したストレス要因に対応する力がそもそも本人に備わっているかどうかや、ストレス要因の受け止め方や対処する時の考え方が影響していると考えられます。これまでの人生で身に付けてきたストレスへの対処法や周囲のサポート体制の有無も発症に大きく関わります。
例えば、真面目で責任感が強い方が、明らかにオーバーワークであるにも関わらず、周囲に助けを求めることができずに仕事を抱え込んでしまった結果、適応障害になってしまうケースを外来ではよくみかけます。
適応障害の治療方法と専門医への相談タイミング
適応障害の治療は、一つの方法に頼るのではなく、複数のアプローチを組み合わせることが一般的です。
休養と環境調整
最も重要なのは、可能な限り早くストレス要因から離れ、心身を休ませることです。そのためには、環境調整が欠かせません。例えば、配置部署を変えてもらう、いったん休職するなどがあげられます。ただ、ストレス要因の種類によっては簡単には離れられないものもあるでしょう。どのように環境調整していくかについては、主治医や家族と相談しながら実現可能な方法を模索していくのがよいでしょう。
ストレスへの対応力を高める
環境調整でストレス要因をうまく取り除けた場合でも、今後再び新たなストレス要因に向き合わなければならないときがあります。また、環境調整だけでストレス要因を軽減することが難しいこともありますので、自身のストレスへの対応力をなるべく高めていき、再び適応障害にならないよう工夫していくことが大切です。
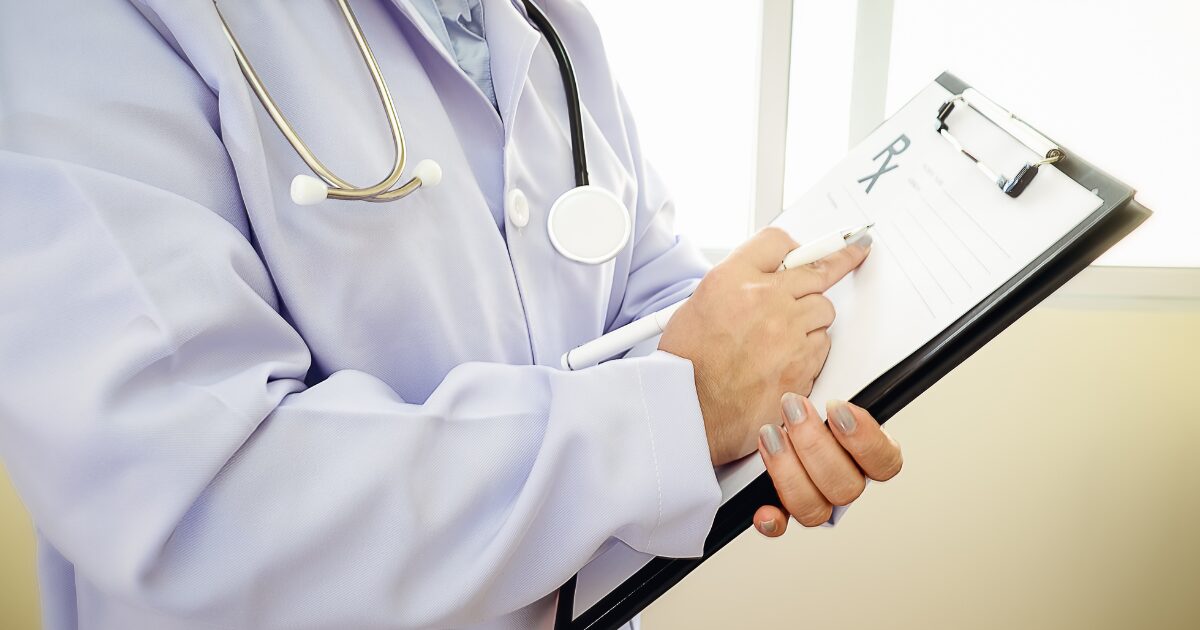
その一つの方法として、認知行動療法(CBT: Cognitive Behavioral Therapy)があります[3]。CBTでは、医師や臨床心理士とのカウンセリングを通して、自分自身の思考や行動パターンに気づき、少しずつ考え方を変えていきます。例えば、「失敗したらどうしよう」というネガティブな思考を、「失敗しても大丈夫」という現実に即した考え方に変えていく練習をします。
CBTにより、ストレス要因に対する考え方や対処法を修正していくことで、ストレス要因への適応力を高められる可能性があります。
当メディアを運営するマインドバディでは、オンラインで認知行動療法を専門としたカウンセリングを提供しています。専門家と一緒にネガティブな思考を見直したい方やストレスへの適応力を高めたい方は詳細を確認してみてください。
薬物療法
適応障害そのものを治す薬はありませんが、不眠や不安感といった症状を緩和するために、抗不安薬や抗うつ薬が補助的に用いられることがあります。適応障害の症状が強い場合に、一時的に薬物療法を行うことで、環境調整に取り組む余裕が生まれます。
どの治療法が合うかは、患者さんによって異なります。ご自身の性格や考え方、置かれている環境を総合的に考え、自分に合った解決策を探っていくことが大切です。
受診すべきタイミングと医療機関の選び方
適応障害が疑われる症状が2週間以上続く場合は、うつ病に進展している可能性もありますので、できるだけ早く専門医(精神科・心療内科)に相談しましょう。特に、日常生活や社会生活に著しい支障が出ている場合や、「死にたい」と感じるほどつらい場合は、早急な受診が必要です。自分の感覚で「何かおかしいな」と思った時点で、迷わず受診することが大切です。
精神科医・心療内科医は、治療のパートナーとなる大切な存在です。診断結果や治療方針を分かりやすく説明してくれる医師を見つけることが重要です。精神科専門医、精神保健指定医の資格の有無は、標準的な診断・治療ができるかどうかのひとつの判断材料となります。
治療の流れと改善までの期間
適応障害の治療は、大まかに次のような流れで進むのが一般的です。症状の程度や生活環境、就労環境、ストレス要因によって治療開始から終結までの期間は様々です。最善の方法がとれるよう、主治医や家族と話し合いながら治療をすすめていくことが大切です。
適応障害の治療の流れ
①医療機関受診(診断)
↓
②治療方針決定(休息期間、ストレス要因を軽減するための環境調整の方針、薬物療法や認知行動療法)
↓
③症状改善
↓
④社会復帰
よくある質問と回答
Q:適応障害は治るの?
ストレス要因に対する対応が的確になされれば、数カ月以内に適応障害は改善します。ただし、ストレス要因が十分解消されていなかった場合は、うつ病などの精神疾患へ移行するリスクも指摘されているため、十分なサポートと経過観察が大切です。
Q:周囲の人はどう接するべき?
話を聞くときは、悩みや不安について無理に聞き出そうとせず、傾聴するようにしましょう。本人の気持ちになるべく寄り添い、無理強いや否定をせず、安心して休める環境を作る手助けをしましょう。
Q:仕事は続けられる?休職の判断基準は?
適応障害で仕事を続けられるかどうかは、ストレス要因や症状の程度、生活環境、就労環境によります。症状が軽度の場合は、業務調整やサポートを受けながら働き続けることも可能ですが、強いうつ状態にあるなどで日常業務や生活に支障が出ている場合は、休職が望ましい場合があります。
休職の判断基準として、日常業務や生活に支障が出ている場合や、うつ症状が目立ち医師が「休養が必要」と判断した時などがあげられます。無理に出勤を続けると、症状の悪化や長期化が懸念されますので、早めに専門医へ相談することが重要です。
まとめ
適応障害は、明確なストレス要因がきっかけで発症し、誰にでも起こり得る病気です。原因となるストレス要因を適切に把握し、環境調整やカウンセリング、必要に応じた薬物療法などを組み合わせることで回復への道が開けます。
「少しおかしいかも」と感じた段階で専門医に相談することが、症状の悪化を防ぐ大きな一歩になります。無理に抱え込まず、周囲や医療機関を上手に頼りながら、自分自身に合ったペースで心身を整えていくことが大切です。
参考文献
[1]適応障害|MSDマニュアル
[2]日本における「適応障害」患者数の増加|社会政策学会誌『社会政策』第12巻第2号
[3]認知行動療法(CBT)とは|認知行動療法センター





